
舞台へ向かうフルトヴェングラー登場の足音、盛大な拍手、演奏前のフルトヴェングラーの言葉が収録されているテープからCD化。
○聴き疲れのしないやわらかな音色。
○ヒスノイズが聴こえるが気になるレベルではない。
○音質の評価を超えた情報量があるように感じられる。
△音の輪郭が甘く、ややぼやけた感じになっている。
バイロイトの第九
OTAKEN RECORDS TKC-301の
復刻は本当に最高なのか!?
はじめに
最初から挑発的なタイトルで恐縮である。そもそも「本当に最高なのか!?」なんて問うても「正しい答え」など存在しない。しかしである「正しい答え」が存在しないから問うことじたいがナンセンスなのか?
つまり挑発的なタイトルの方が目立つ!注目をあびる!喰い付きがよい!それだけのことである。
そもそもの発端は次のような宣伝を目にしたからである。
| クラシック通販ショップ「アリアCD」より~抜粋~ |
| 初期HMV.1stフラットプレス、ミント盤を高音質復刻!
世の中には夢のような話が現実になることがあるものです、英製と同レーベルデザイン同プレス規格と思われる豪HMV初期1stフラットプレスのミント盤が発見されたのです。 レーベルヒゲ(*1)の皆無はもちろんのこと2楽章の極浅キズ以外はプレス工場から今あがって来たかのようなほれぼれするような立体的盤面です。ともかく通針の形跡がほとんど感じられず後にも先にもこのようなHMV初期フラット盤は他にないのではないでしょうか? 今までに聴いたことのないすぐれた音質のバイロイト盤であることは言うまでもないことです。百聞は一聴にしかず、フルトヴェングラー・ファンの方はもちろんすべてのクラシックファン必聴の音源です。(オタケンレコード 太田憲志) |
| (*1)レーベルヒゲとは、レコードを鳴らすときターンテーブルの中心棒にレコードの中心孔をはめ込むが漠然とレコードをあてがって盤をあちこちにずらしてはめ込むとレーベル面にヒゲのような痕跡が残る。 レーベルヒゲがあるとレコードを大切に扱っていない所有者の証として査定額が安くなるのである。また、レーベルヒゲの有無によって通針の程度が推し測られる。 |
注意書き:
音質評価は、100%私の主観的かつ嗜好での判断です。
音質評価については,特定のメーカーや個人を支持したり非難す意図は100%ありません。話のネタです。
そもそも、音質の評価は再生装置の違い、個人の嗜好、演奏に対する共感度などなど、いろいろな要素が複雑に絡み合い評価が別れるものです。
例えば、CLASSIC PRESS誌(休刊)で平林直哉氏と福島章恭氏の両氏が復刻CDの音質評価をする記事が連載されましたが、しばしばその評価は食い違いを見せました。
当然の結果として私と異なる意見や感想を抱く人も居るでしょう。私はそれらの人々と意見の一致をはかる必要はないと考えています。違いは違いとして認めるのが私の姿勢です。
話のネタとしてお付き合いください。
録音データ:
・ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」
エリーザベト・シュヴァルツコップ(ソプラノ)
エリーザベト・ヘンゲン(アルト)
ハンス・ホップ(テノール)
オットー・エーデルマン(バス)
バイロイト祝祭管弦楽団&合唱団
ウィルヘルム・フルトヴェングラー(指揮)
1951年7月29日 バイロイト祝祭劇場
・戦後再開されたバイロイト音楽祭初日の記念演奏会でのライヴ録音。
・同曲の録音の中で評論家、一般のファン(*2)ともにベストの録音、名演として評価されている。
(*2)音楽之友社 ONTOMO
MOOK リーダーズ・チョイス―私の愛聴盤―読者が選ぶ名曲名盤100(2002年発行)音楽之友社 ONTOMO
MOOK 21世紀の名曲名盤―① 究極の決定版100(2002年発行)を基ネタとしている。
●感想
手元にある東芝EMI TOCE-6510聴き比べると、ベールを剥がしたような輪郭のクッキリとした音があらわれた。クリアーな音のひとつひとつにパワーが宿りフォルティシモでの歪みも少なくなっている。音質が向上しているのは明々白々であった。
ところがである!
音質向上イコール感動の向上につながらないのである。最初は何度も聴いた録音なので私自身の新鮮な気持ちが薄らいでいるのか?飽きているのか?とも思ったが・・・・・・・・
しかし!
両盤にじっくりと耳を傾けると、明らかに音質の劣る東芝EMI
TOCE-6510盤の方が音楽の感動というか、微妙なニュアンスというか、ストレートに言ってしまうと「すばらしい演奏」に感じられるのである。
●両盤の比較
|
東芝EMI TOCE-6510 舞台へ向かうフルトヴェングラー登場の足音、盛大な拍手、演奏前のフルトヴェングラーの言葉が収録されているテープからCD化。 ○聴き疲れのしないやわらかな音色。 ○ヒスノイズが聴こえるが気になるレベルではない。 ○音質の評価を超えた情報量があるように感じられる。 △音の輪郭が甘く、ややぼやけた感じになっている。 |
| TKC-301と比較すると離れた場所にあるマイクから収録した感じになっている。 | |
| 写真に例えると、被写体である女優のピントは甘くなっているが背景の海辺の美しさも残している。 | |
|
OTAKEN RECORDS
TKC-301 英製と同レーベルデザイン同プレス規格と思われる豪HMV初期1stフラットプレスのミント盤OALP-1286-7からの盤起しCD。 ○音の輪郭がクッキリと再現される。 ○LPのスクラッチノイズがハッキリ聴こえる。各楽章の冒頭は耳に付くが次第に気にならなくなる。 △LPから起しているためか?マスターテープから情報引き出しに限界が感じられる。 △身の詰まったパワフルな音色あるが、やや大味に感じられる。 △音色がやや硬く少々聴き疲れする。 |
| TOCE-6510と比較すると接近した場所にあるマイクから収録した感じになっている。 | |
| 写真に例えると、被写体である女優にピントを合わせて背景は無地の証明写真。 | |
●おまけ
2枚だけの比較では物足りないので図書館で借りたCDも加えてみた。
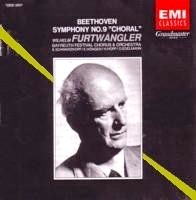 |
東芝EMI TOCE-3007 ドイツ・エレクトローラ社によるブライトクランク・ステレオ(モノーラル音源を人工的にステレオ加工を施したもの)盤 20bit 88.2kHz Mastering HS-2088盤 ○身の詰まったパワフルな音。 △音の拡がりが増し細部もクッキリとしている。 ×ヒスノイズが盛大に聴こえ、わずらわしい。 ×電気的な音色になっている。 ×明るい音色で軽いフルトヴェングラーに変身している。 ×フォルティシモで濁と癖のある音色に変わり鑑賞の妨げとなる。 |
| モノーラル録音をステレオ化する試みを否定しないがヒスノイズが増大、フルトヴェングラーらしからぬ明るい音色に変わり、拡がりが増しているのに細部はクッキリとしている不自然さに違和感を覚えた。 | |
| 写真に例えると、被写体である女優が厚化粧によってグロテスクに変身。 | |
私の勝手な想像であるが、このブライトクランク・ステレオはLP時代にステレオ加工したテープをそのままCD化したのではないだろうか?盛大に聴こえ、わずらわしいヒスノイズを聞くと現代の技術ならもっと抑えられる気がする。
音の拡がりを生み出すエコー加工も音の輪郭がクッキリとしたまま音量のみが小さくなる不自然なエコーで、なによりもフルトヴェングラーらしい重量感のある響きが軽量化されたように聴こえる。
現代の技術を駆使すれば、より自然で、フルトヴェングラーの持ち味を生かしたステレオ加工が出来ると思うが・・・・誰か挑戦しませんか?