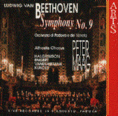 ●ベートーヴェン 交響曲 第9番
●ベートーヴェン 交響曲 第9番ペーター・マーク指揮
パドヴァ・エ・デル・ヴェネト管弦楽団
アマンダ・ハルムグリンソン(ソプラノ)
ルートヒルド・エンゲルト(メゾ・ソプラノ)
ツェーガー・ヴァンデルステーネ(テノール)
フリードマン・クンダー(バス)
アテスティ合唱団
1994年12月20日パドヴァ・サン・アントニオ大聖堂(ライブ録音)
ARTS 47248−2(輸入盤)
私は、山あり谷あり、感情移入型の演奏が好きですが・・・・この演奏は私の好みと異なる方向性が多
くありました。
では、聴いていて退屈だったか?というと・・・・これがねー。新鮮な感覚とでも表現しましょうか、新たな
感覚・感触の第九を聴けた感じがしました(とエラソーに恥ずかしい、他にふさわしい表現が思いつかな
かったのだ)。
第1楽章ですが、私は雄大なスケールと推進力に満ちた演奏が好みで、ついつい、このような演奏を求
めてしまうのですが・・・・
このCDの演奏は私の好みとやや異なりテンポも中庸(悪い意味じゃないよ)な感じです。しかし、ティンパ
ニーの生かし方、低弦楽器の突き出し(バッソオスティナートが印象的)、スタッカートの付け方などの新鮮
な感覚!104〜105小節のようなパッセージでのテンポの落とし方の神経のこまやかさ!魅力的な演奏
が随所に光ります。
第2楽章の導入句でのズバッとした鋭い切り口。速いキビキビしたテンポでの主題提示。おぉぉ〜ここ
は私好みだ!
また、第2主題が新鮮でした。木管楽器も弦楽器もくっきり聴こえるのですが・・・・それだけではない、
新鮮なものを感じます。何回か繰り返して聴くと低弦楽器をやや強調しているように感じられます。
トリオは私の好みからすると、やや遅い感じがします。しかし、弦楽器が絡らんでくると、私の好など
ぶっ飛ばして音楽が豊かになる。このあたりに神経のこまやかさを感じます。
そして終結部がいいんですよ。最後の3小節をズバッとした鋭い切り口で絞める!爽快の極みです。
第3楽章、導入句は速めのテンポですが、弦楽器が主題を奏でると、すでにテンポが落る感じです。し
かし、そこには感情移入的な感覚でなく極自然な感じであるのが心にくい。
2度のファンファーレは絶叫させず、最終小節の部分の強調も見られない。
しかし、もの足りなさは感じさせない。冒頭に目立つ表現があったので・・・・みょ〜に期待をもってし
まった。
第4楽章、冒頭の咆哮は荒々しく暴力的に響かせて、レシタティーヴォは、あまりテンポを落とさずに進
める。これが私の好みである。
しかし、このCDの演奏では冒頭の咆哮で上品とまでは行かないが、荒々しく暴力的に響くことを嫌うか
のようだ。ところがレシタティーヴォでの押しの強さに驚いてしまった。
92小節から歓喜の主題が現れるが、ちょっとテンポに変化が加えられ、あれ?次もヤルのかな?と注
目してしまう。心にくい表現ですね〜っ。その後、音楽は淀みなく生彩に明朗に進みます。
さて、595小節からAndante maestosoに音楽が変わります。
私は歓喜の歌より、ここが好き!大宇宙の神秘を感じさせます(ちょっと気恥ずかしい表現)。ここで冒
頭のフォルティシモにアクセントを加えて熾烈な感じを出して音楽が変わった!と実感させる効果を挙げ
ている。
655小節からAllegro energivo 壮大なフガートになりますが指揮者によってテンポが大いに異なる部
分です。
速いテンポではまさしくエネルジーコの音楽になり、遅いテンポでは595小節からの流れを引き継ぐ神
秘的な音楽になります。
私の好みは後者ですが、このCDの演奏は前者です。
壮大なフガートが終わり748小節からのBruder!で滋しむようにテンポが落ちるのは驚きました。
コーダでは916小節のMaestosoでかなりテンポを落としています。また918小節schonerのnerで独自の
効果が聴けます。どうやったのだろう?
最後の最後936小節で若干テンポを落としているようで、これまた、独自の効果が聴けます。
些細なことであるがパドヴァ・サン・アントニオ大聖堂の残響が消えてから拍手が起こるのは聴衆のマ
ナーのよさを感じさせます(私はフライング・ブラヴォーが大嫌だ!)。
また、ジャケットの写真を見ると合唱団が前列に女声、後列に男声が配置されており、CDを聴くと男女が
左右に別れない響きに新鮮さを感じます。またソプラノとアルト,テノールとバスも左右に別れていないよう
に響きます。どんな配置だったんだろう?
00/01/17
前に戻る ホームに戻る