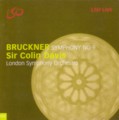
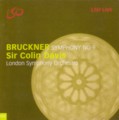
●ブルックナー 交響曲 第9番
サー・コリン・ディヴィス指揮/ロンドン交響楽団
録音2002年 2月22〜24日
LSO LIVE(LSO自主製作) LSO 0023 (輸入盤)
ブルックナーを録音しないと人気がでない某外資系CDショップのフリー・ペーパーにこんな皮肉が書かれていた。
サー・コリン・ディヴィスのブルックナーはオルフェオレーベルに録音した7番の他、海賊盤では6番があるだけあった。
仮にこの録音がメジャー・レーベルで発売されれば”最後の巨匠ついにブルックナー第九を録音”などと仰々しいコピー
で売り出されただろう。
ズバッと言おう”私はこの録音を聴いてすばらしい感銘を受けた”私は年間60〜70枚ほどCDを購入するがCDを聴
いてこれほどの感銘を受けるのは年に1回あるか?ないかである。これがあるから苦しい家計をやりくりして1枚1枚と
ついついCDを買ってしまうのだ。
この録音でまず感じるのは一音一音丁寧に丁寧に積み上げていくような音楽作りで特に第1楽章は遅めのテンポ
(28分強)と相まってじっくり構えた演奏に感じられる。そして遅いテンポでありがちな重々しい雰囲気や緩みはいっさ
いなく音楽は常に僅かづつであるがテンションがあがって行く。そう!これがコリン・ディヴィスの特徴で一見(聴)地味
なようで、その奥には僅かづつ膨れ上がるテンションがあり、深い世界が広がっているのだ!
またブルックナー特有の金管の強奏も派手さはなく地味で抑制気味に感じるが、それがまたプラスに作用して深み
や奥行きを与える。さすが巨匠!サー・コリン!と言いたくなる。
第2楽章は第1楽章は同様な丁寧な積み上げを感じさせるが、その中でスケルツォの楽想にふさわしいメリハリやキ
レを描いている。堅実・中庸のイメージの強いコリン・ディヴィスであるがトリオでの大きな間とその後の超々スローーー
テンポが聴ける。ここまでヤルのか!とビックリさせられる。
第3楽章は方向性が変わり表現意欲を感じさせる。随所に豊かな感情に溢れたフレージングを聴かせこの曲のもつ
宗教的な奥深さや神々しい広がりを損なうことなく、さらに深化している。第3楽章だけではないがここで聴かれる弦の
響きはなんと表現しょうか?因みに右手に2ndヴァイオリンを配した両翼配置である。奥行きのある響き、透明な響き、
真摯な響、などなどあらゆる要素が含まれているのである。サー・コリン恐るべし。彼が至高の極み達していたことを思
い知らされる録音であった。
02/11/14
ホームに戻る 前に戻る