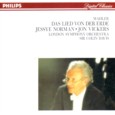 ●マーラー 交響曲 「大地の歌」
●マーラー 交響曲 「大地の歌」コリン・デイヴィス指揮
ロンドン交響楽団
ジョン・ヴィッカーズ(テノール)
ジェシー・ノーマン(アルト)
録音:1981年3月15〜18日
PHILIPS PHCP-9014
「終末への恐怖を超越した清廉な響き。情報量も満載。しめやかに聴かせる<告別>は東洋的観念の境
地だ。永遠に、永遠に、永遠に?ん、歌っての誰だよ!?この媚び媚びノーマンと下品なヴィッカーズのお下
劣コンビ、《大地の歌》史上最悪の歌唱なのだ。名指揮者120人のコレを聴け! 洋泉社 P60より」
なかなか刺激的な文章である。実際にCDを再生して耳を傾けると下品・お下劣には思えなかった。元々「大
地の歌」は人間の弱さを赤裸々に叫び、かたる内容であり、お上品な内容ではないし、これでいいんじゃない
のかな?・・・・それとも<お下劣>は演奏とは別の意味があるのだろうか?
マーラー「大地の歌」は強烈な音楽である。私が初めて聴いたのは学生時代であった。すぐに好きな曲になっ
たが、その強烈な赤裸々な内容に何度も気軽に聴ける曲ではなかった。
デイヴィスの演奏はそんな初めて聴いた強烈な印象を蘇らせるに充分な内容であった。「大地の歌」の顔に
当たる第1楽章は速いテンポとヴィッカーズの熱唱で、それほど過激な表現をしていないが充分ドラマチックな
印象を受ける。第3楽章の「青春について」は、かなり速めのテンポでリタルダント(テンポを徐々にゆっくりに
する)も控えめでサッと駆け抜ける印象で、それがはかない青春の寂しさを表しているように感じる。
第4楽章の「美について」は遅いテンポで丁寧にじっくり仕上げている印象で、遅いテンポとノーマンの抑制を
利かせた声、止まるようなリタルダントによって前半部は時間が止まっているような風景が広がっている。中間
部は徐々にテンポを上げてゆくコントロールのよさ、ティンパニの強打を徐々に音量を上げるなど芸の細かさ
が冴える。
そして95小節と96小節の間にルフト・パウゼ(総休止の間)!が異常なほど長く、冒頭の旋律との対比を際
立たせている。そしてコーダに向かってゆっくりと流れてゆく。すると対比的な第5楽章を迎える。
ここで気が付いた!テノールとアルトの対比を明確に描き分けている!
第6楽章は「告別」はゆっくりとしたテンポで流れてゆく演奏時間35分弱。第4楽章同様にノーマンの抑制した
歌を伴ってオケをじっくり丁寧にコントロールし仕上げている印象であった。
04/10/25
前に戻る ホームに戻る